
学力は「ごめんなさい」にあらわれる (ちくまプリマー新書 466)
学力は「ごめんなさい」にあらわれる (ちくまプリマー新書 466)
勉強が苦手な原因は”ことば”のズレにある!
- 人の話はしずかに黙って聞く
- すらすらと本を読むのは得意だ
- 問題が解けるとうれしくて仕方ない
こんな人はズレているかもしれません
と読みたくなるような帯がついたこの本は、ダイヤモンド・オンラインでも紹介されており、とても納得のいく内容でした。
日々の言葉のやりとりが、全ての学びを支えている。何気ないやりとりを通じて、子どもは多くの価値観を学んでいる。目の前にある子どもの姿は言葉の教育の集大成といっても過言ではありません。
「やばい」は便利なことばで、肯定的にも否定的な意味でも使える。その結果、思考せずに使いがち。
品位の問題だけではなく、考える習慣を作る意味でも言葉遣いを正す意味がある。
挨拶の習慣がない子は相手意識が希薄で、自己中心的に物事を捉えることを優先しがち。挨拶は成長へのきっかけや、運命をかえるかけがえのないもの。だから、「おはようございます」といった数だけ、可能性は広がる
(3章より)
人の記憶は1G程度しかないそうですが、言葉を通して圧縮して情報を記憶できると思われます。ところが、その言葉が貧弱になり、すべて「やばい」だけで表現されると、危険な香りしかしません。互いのコミュニケーションですら、うまくいかなくなりそうです。言葉は文化なので、変わっていくのは必然なのですが、どうやら、豊かな感情表現が失われていくことに危機感を感じたりします。
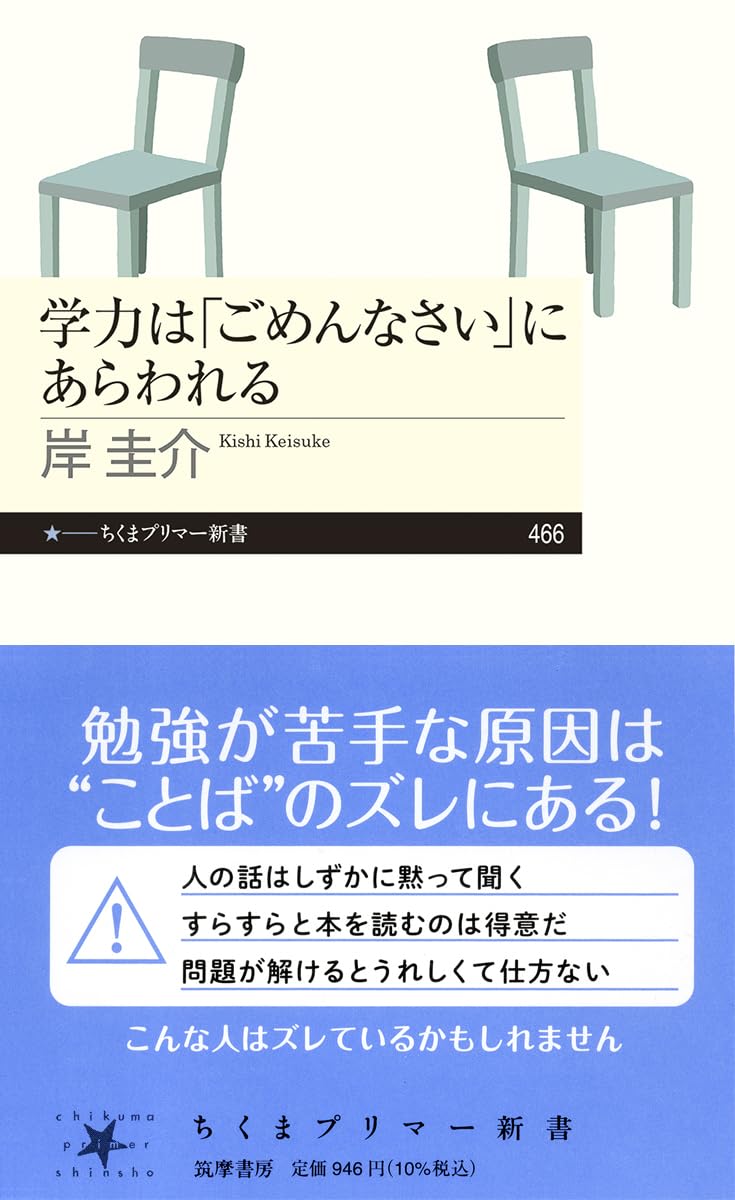
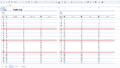

コメント